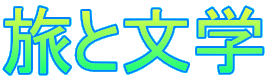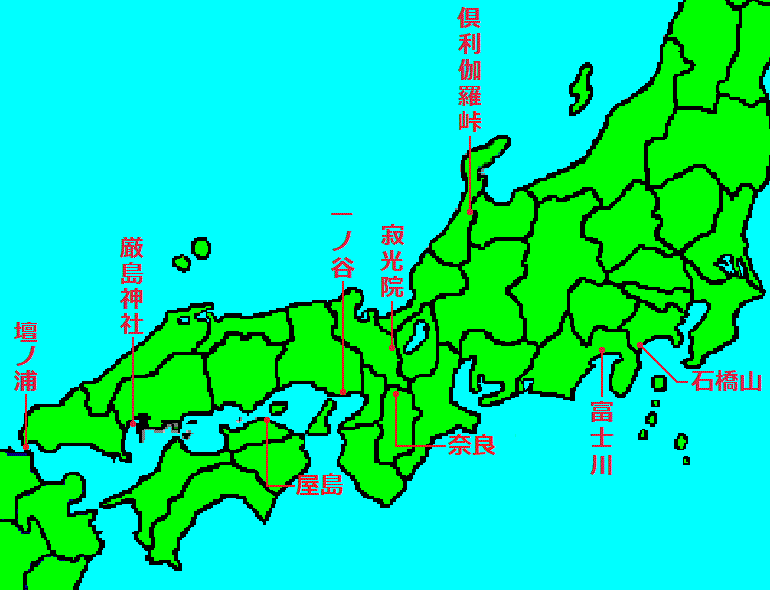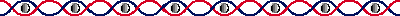
「祇園精舎の鐘の聲、諸行無常の響きあり。」で始まる『平家物語』は、平清盛を中心とした平家一門の栄華から滅亡までの源平合戦を描いた軍記物語です。歴史的事実を描いた反面、フィクションも盛り込まれていまが、軍記物語中の最高の作品で、日本文学の中でも重要なものです。著者は信濃前司行長で、鎌倉時代前期の成立とされていますが、はっきりしません。盲目の琵琶法師による平曲(平家琵琶)にのせた独特の語りによって、世間に流布され、広く国民の中に浸透していったのです。
『平家物語』は平家一門の栄華から筆を起こしていますが、その後の源平合戦が話の中心で、これを巡ることは必然的に、源平の戦跡を回ることになります。前半の源氏の挙兵から京の都へ攻め上るところも興味深いのですが、平氏が都を落ち延びる後半の部分に哀惜があり、西日本にその場面を訪ねて旅した時にとりわけ、「盛者必衰の理」を感じ取ることができます。一ノ谷、屋島、壇ノ浦と平氏が次々と負けて敗走していく情景が走馬燈のように浮かんでくるのです。
私は、今までに、『平家物語』の足跡を訪ねる旅に何度か出ていますが、その中で心に残った所を9つ、物語の順に紹介します。
(1) 厳島神社<広島県廿日市市>
平安時代の寝殿造りの粋を極めた建築美で知られる日本屈指の名社です。『平家物語』にも、平清盛が厳島神社に関わるようになった由来を書いた“大塔建立”以外にも、“徳大寺厳島詣”、“卒都婆流”、“厳島御幸”などに厳島のことが出てくるのです。平家の氏神としてあがめられ、その権勢最盛期を象徴する国宝建造物で、平家の栄華の一端を見る思いがするのです。有名な、舞楽が始まったのもこの時代からといわれています。廻廊で結ばれた朱塗りの社殿は、潮が満ちてくるとあたかも海に浮かんでいるように見えるのです。全国に約500社ある厳島神社の総本社で、1996年(平成8)には、ユネスコの世界遺産(文化遺産)にも登録されました。また、ここに収められている「平家納経」は、平安時代後期の1164年(長寛2)厳島神社に平清盛が奉納した全32巻の経典で、それに清盛の願文を加えた33巻が完在し、1954年(昭和29)に国宝となっています。それらは、宝物館で見ることができます。
大塔建立(巻第三)
・・・・・・・・
抑も平家安芸厳島を、信じ始られける事はいかにと云ふに、清盛公未だ安芸守たりし時、安芸国を以て、高野の大塔修理せられけるに、渡辺遠藤六郎頼方を雑掌に付られたり、六年に修理終りぬ。修理終りて後、清盛高野へ上り、大塔拝み、奥院へ参られたりけるに、何処より来たるともなく、白髪なるが、眉には霜を垂れ、額に波を畳み、鹿杖の二股なるにすがつて、来給へり。この僧何となう物語をしけるほどに、「それ我が山は、昔より密宗を控へて退転なし。天下にまたも候はず。大塔既に修理終り候ひぬ。それにつき候ひては、越前の気比宮と安芸の厳島は、両界の垂迹にて候ふが、気比宮は栄えたれども、厳島は無きが如くに荒れ果てて候ふ。あはれ同じうは、この序でに奏聞して、修理せさせ給へかし。さだにも候はば、官加階は肩を並ぶる人、天下にもまたあるまじきぞ」とて立たれけり。
この老僧の居給へる所に、異香即ち薫じたり。人を付けて見せらるるに、三町ばかりは見え給ひて、その後は掻き消すやうに失せ給ひぬ。これ只人にあらず、大師にてましましけり、といよいよ尊く覚えて、娑婆世界の思ひ出にとて、高野の金堂に曼陀羅を書かれけるが、西曼陀羅をば、常明法印といふ絵師に書かせらる。東曼陀羅をば、清盛書かんとて、自筆に書かれけるが、八葉の中尊の宝冠をば、いかが思はれけん、我が首の血を出だいて書かれけるとぞ聞えし。その後都へ上り院参して、この由を奏聞せられたりければ、君も臣も御感ありけり。
なほ任を延べて、厳島をも修理せらる。鳥居を建て替へ社々を造り替へ、百八十間の廻廊をぞ造られける。修理終りて後、清盛厳島へ参り、通夜せられたりける夢に、御宝殿の御戸押し開き、鬢結うたる天童の出でて、汝この剣を以て、朝家の御固めたるべし」とて、銀の蛭巻したる小長刀を賜はるといふ夢を見て、覚めて後見給へば、現に枕上にぞ立たりける。さて大明神御託宣ありて「汝知れりや忘れりや。ある聖を以て云はせし事は、但し悪行あらば子孫までは叶ふまじきぞ」とて大明神上がらせ給ひけり。めでたかりし事共なり。
流布本『平家物語』 より |
|
 |
 |
| 厳島神社の鳥居 |
厳島神社の客社祓殿 |
(2) 石橋山<神奈川県小田原市>
1180年(治承4)8月に、伊豆に流されていた源頼朝と平氏方の大庭景親らとが戦った石橋山の戦い(源平合戦の一つ)が行われたところです。小田原市南部にあり、この周辺で源頼朝軍300騎と大庭景親ら3,000余騎が戦ったのですが、多勢に無勢で源頼朝軍の大敗に終わり、敗走した源頼朝は山中に逃げ込み、船で安房国へ落ち延びることになりました。戦いのあった場所に石橋山古戦場の碑が立ち、近くにこの戦いで死んだ佐奈田与一を祀る佐奈田霊社と与一塚や同じく戦死した陶山文三家康を祀る文三堂などがあります。
大庭早馬(巻第五)
・・・・・・・・
「去らんぬる八月十七日、伊豆国の流人、前右兵衛佐頼朝、舅北条四郎時政を語らうて、伊豆国の目代和泉判官兼隆を、山木が館にて夜討ちに討ち候ひぬ。その後土肥・土屋・岡崎を始めとして三百余騎、石橋山にたて籠って候ふ処を、景親、御方に志を存ずる者ども、一千余騎を引率して、おし寄せてさんざんに攻め候へば、兵衛佐わづか七八騎に討ちなされ、大童に戦ひなって、土肥の杉山へ逃げ籠り候ひぬ。畠山、五百余騎で御方を仕る。三浦大介が子ども、三百余騎で源氏方をして、由井・小坪の浦で攻め戦ふ。畠山、軍に負けて、武蔵国へ引き退く。その後畠山が一族、川越・稲毛・小山田・江戸・葛西惣じて七党の兵ども、ことごとく起こり合ひ、都合その勢二千余騎、三浦衣笠の城におし寄せて、一日一夜攻め候ひし程に、大介討たれ候ひぬ。子どもは皆、九里浜の浦より船に乗って安房・上総へ渡り候ひぬとこそ、人申しけれ」
・・・・・・・・
流布本『平家物語』 より |
|
 |
 |
| 石橋山古戦場碑(神奈川県小田原市) |
佐奈田霊社の社殿 |
(3) 富士川<静岡県富士市>
源平の古戦場の一つで、1180年(治承4)10月に源頼朝・武田信義軍と平維盛軍が、富士川の河口付近で戦ったのです。夜陰に乗じて、武田信義の部隊が平家の後背を衝かんと富士川の浅瀬に馬を乗り入れると、水鳥が反応し一斉に飛び立ちました。これに驚いた平家方は大混乱に陥って、敗走したといわれています。戦の後で、離れ離れになっていた源頼朝と義経の劇的な対面があったと言われています。
富士川(巻第五)
・・・・・・・・
さる程に、同じき二十四日の卯の刻に、富士川にて源平の矢合はせとぞ定めける。二十三日の夜に入って、平家の兵ども、源氏の陣を見渡せば、伊豆・駿河の人民百姓らが、軍に恐れて、或いは野に入り山に隠れ、或いは舟に取り乗って、海河に浮かびたるが営みの火の見えけるを、
「あなおびただし源氏の陣の遠火の多さよ。げにも野も山も海も河も、みな武者でありけり。いかがせん」
とぞあきれける。その夜の夜半ばかり、富士の沼にいくらもありける水鳥どもが、何にかは驚きたりけん、一度にばっと立ちける羽音の、雷大風などのやうに聞こえければ、平家の兵ども、
「あはや源氏の大勢の向かうたるは、昨日斎藤別当が申しつるやうに、甲斐・信濃の源氏ら、富士の裾より、搦手へや廻り候ふらん。敵何十万騎かあるらん。取り籠められては叶ふまじ。ここをば落ちて、尾張河・洲俣を防げや」
とて、取る物も取り敢へず、我先に我先にとぞ落ち行きける。余りにあわて騒いで、弓取る者は矢を知らず、矢取る者は弓を知らず、我が馬には人乗り、人の馬には我乗り、繋いだる馬に乗って馳すれば、株をめぐる事限りなし。その辺近き宿々より、遊君遊女ども召しあつめ、遊び酒もりけるが、或いは頭蹴破られ、或いは腰踏み折られて、喚き叫ぶ事おびただし。
・・・・・・・・
流布本『平家物語』 より |
|
 |
 |
| 富士川の古戦場に立つ平家越の碑 |
源頼朝と義経が腰かけた対面石(清水町八幡神社) |
(4) 奈良(南都)<奈良県奈良市>
治承4年12月28日(1181年1月15日)に、平清盛の命により、平重衡らの平氏軍が、奈良(南都)の東大寺・興福寺等の仏教寺院を焼き討ちにした事件が起きます。平氏政権に対して反抗的な態度を取り続ける奈良(南都)勢力の東大寺・興福寺等に対する戦闘でした。平清盛の命を受けた平重衡を総大将とした平氏軍は、治承4年12月25日に奈良(南都)へ向かい、28日には奈良坂・般若寺に城郭を築いて待ちかまえる衆徒を突破して奈良へ攻め入ります。激戦が繰り広げられた後、夜になって火がかけられ、その戦火が興福寺や東大寺等にも拡大し、奈良の大仏や多くの寺院が焼失、『平家物語』では、大仏殿の二階に逃げ込んだ人たちはじめ、計3千5百余人が焼死したと記しました。また、奈良(南都)勢力の戦死者は千余人とされています。この戦火によって、東大寺・興福寺など奈良(南都)の仏教寺院の多くが焼失しましたが、春日神社や新薬師寺などは免れました。『平家物語』を訪ねて
奈良を訪れた時、東大寺の転害門を見ると永覚の奮戦を思い、大仏殿に入るとここで焼死した1,700余人の老若男女や焼け落ちた大仏を偲び、猿沢の池に至れば、池の端に並べられた60余の首に哀れを感じざるを得ません。
奈良炎上(巻第五)
都にはまた、「南都三井寺同心して、あるひは宮受け取り参らせ、あるひは御迎ひに参る条、これもつて朝敵なり。しからば奈良をも攻めらるべし」と聞こえしかば、大衆大きに蜂起す。関白殿より、「存知の旨あらば、幾度も奏聞にこそ及ばめ」とて、右官の別当忠成を下されたりけるを、大衆起こつて、「乗り物より捕つて引き落とせ、髻切れ」とひしめく間、忠成色を失ひて逃げ上る。次に右衛門の督親雅を下されたりけれども、これをも、「髻切れ」とひしめきければ、取るものも取り敢へず、急ぎ都へ上られけり。その時は勧学院の雑色二人が髻切られてけり。南都にはまた大きなる球打の玉を作りて、これこそ入道相国の首と名付けて、「打て、踏め」などぞ申しける。「言葉の洩らし易きは、災を招く仲立ちなり。言葉の慎まざるは、敗れを取る道なり」と言へり。懸けまくも忝く、この入道相国は、当今の外祖にておはします。それをかやうに申しける南都の大衆、およそは天魔の所為とぞ見えし。
入道相国、且つ且つ先づ南都の狼藉を鎮めんとて、妹尾の太郎兼康を、大和の国の検非所に補せらる。兼康五百余騎で馳せ向かふ。「相構へて、衆徒は狼藉をいたすとも、汝らはいたすべからず。物の具なせそ、弓箭な帯せそ」とて遣はされたりけるを、南都の大衆、かかる内儀をば知らずして、兼康が余勢六十余人搦め捕つて、一々に首を斬つて、猿沢の池の傍にぞ掛け並べたりける。入道相国大き怒りて、「さらば南都をも攻めよや」とて、大将軍には、頭の中将重衡、中宮の亮通盛、都合その勢四万余騎、南都へ発向す。南都にも老少嫌はず七千余人、兜の緒を締め、奈良阪、般若寺、二箇所の道を掘り切つて、掻楯掻き、逆茂木曳いて待ちかけたり。平家四万余騎を二手に分かつて、奈良阪、般若寺、二箇所の城郭に押し寄せて、時をどつとぞ作りける。大衆は徒立ち打ち物なり。官軍は馬にて駆け回まはし駆け回し攻めければ、大衆数を尽くして討たれにけり。卯の刻より矢合はせして、一日戦ひ暮らし、夜に入りければ、奈良阪、般若寺、二箇所の城郭ともに敗れぬ。落ち行く衆徒の中に、坂の四郎永覚と言ふ悪僧あり。これは力の強さ、弓矢打ち物取つては、七大寺十五大寺にも勝れたり。萌黄威の鎧に、黒糸威の腹巻二両重ねてぞ着たりける。帽子兜に五枚兜の緒を締め、茅の葉の如くに反つたる白柄の大長刀、黒漆の大太刀、左右の手に持つままに、同宿十余人前後左右に立て、転害の門より討つて出でたり。これぞしばらく支へたる。多くの官兵ら馬の脚薙がれて、多く亡びにけり。されども官軍は大勢にて、入れ替へ入れ替へ攻めければ、永覚が防ぐところの同宿皆討たれにけり。永覚心は猛う思へども、後ろ疎らになりしかば、力及ばず、ただ一人南を指してぞ落ち行きける。
夜戦になつて、大将軍頭の中将重衡、般若寺の門の前にうつ立つて、暗さは暗し、「火を出だせ」とのたまへば、播磨の国の住人、福井の庄の下司、次郎大夫友方と言ふ者、楯を割り松明にして、在家に火をぞかけたりける。頃は十二月二十八日の夜の、戌の刻ばかりのことなれば、折節風は激し、火元は一つなりけれども、吹き迷ふ風に、多くの伽藍に吹きかけたり。およそ恥をも思ひ、名をも惜しむほどの者は、奈良阪にて討ち死にし、般若寺にして討たれにけり。行歩に適へる者は、吉野十津川の方へぞ落ち行きける。歩みも得ぬ老僧や、尋常なる修学者、稚児ども女童部は、もしや助かると、大仏殿の二階の上、山階寺の内へ、我先にとぞ逃げ入りける。大仏殿の二階の上には、千余人登り上がり、敵の続くを上せじとて、橋を引きてげり。猛火は正しう押しかけたり。喚き叫ぶ声、焦熱、大焦熱、無限阿鼻、炎の底の罪人も、これには過ぎじとぞ見えし。
興福寺は淡海公の御願、藤氏累代の寺なり。東金堂におはします仏法最初の釈迦の像、西金堂におはします自然涌出の観世音、瑠璃を並べし四面の廊、朱丹を交へし二階の楼、九輪空に輝きし二基の塔、たちまちに煙となるこそ悲しけれ。東大寺は常在不滅、実報寂光の生身の御仏と思し召し準へて、聖武皇帝、手づから自ら磨きたて給ひし金銅十六丈の盧遮那仏、烏瑟高く顕はれて、半天の雲に隠れ、白毫新たに拝まれさせ給へる満月の尊容も、御首は焼け落ちて大地にあり、御身は沸き合ひて山の如し。八万四千の相好は、秋の月早く五重の雲に隠れ、四十一地の瓔珞は、夜の星むなしう十悪の風にただよひ、煙は中天に満ち満ちて、炎は虚空に隙もなし。まのあたり見奉る者はさらに眼をあてず、かすかに伝へ聞く人は、肝魂を失へり。法相三論の法文聖教、すべて一巻も残らず。我が朝は申すに及ばず、天竺震旦にもこれほどの法滅あるべしとも思えず。優填大王の紫磨金を磨き、毘首羯磨が赤栴檀を刻みしも、わづかに等身の御仏なり。いはんやこれは南閻浮提の内には、唯一無双の御仏、永く朽損の期あるべしとも思はざりしに、今毒縁の塵に交はつて、久しく悲しみを残し給へり。梵釈四王、竜神八部、冥官冥衆も、驚き騒ぎ給ふらんとぞ見えし。法相擁護の春日大明神、いかなることをか思しけん、されば春日の野露も色変はり、三笠山の嵐の音も怨むる様にぞ聞こえける。炎の中にて焼け死ぬる人数を数へたれば、大仏殿の二階の上には一千七百余人、山階寺には八百余人、ある御堂には五百余人、ある御堂には三百余人、具に記いたりければ、三千五百余人なり。戦場にして討たるる大衆千余人、少々は般若寺の門に斬り懸けさせ、少々は首ども持つて都へ上られけり。明くる二十九日、頭の中将重衡、南都滅して北京へ帰り入らる。およそは入道相国ばかりこそ、憤いきどほり晴れて喜ばれけれ。中宮、一院、上皇は、「たとひ悪僧をこそ亡ぼさめ、多くの伽藍を破滅すべきやは」とぞ御嘆きありける。日頃は衆徒の首大路を渡いて、獄門の木に懸けらるべしと、公卿詮議ありしかども、東大寺興福寺の滅びぬる浅ましさに、何の沙汰にも及ばず。ここやかしこの溝や堀にぞ捨て置きける。聖武皇帝の宸筆の御記文にも、「我が寺興福せば、天下も興福すべし。我が寺衰微せば、天下も衰微すべし」とぞ遊ばされたる。されば天下の衰微せんこと、疑ひなしとぞ見えたりける。浅ましかりつる年も暮れて、治承も五年になりにけり。
流布本『平家物語』 より |
|
 |
 |
| 猿沢の池 |
東大寺大仏殿 |
(5) 倶利伽羅峠<石川県津幡町・富山県小矢部市>
源平の古戦場の一つで、1183年(寿永2)5月に源義仲軍と平維盛率いる平家軍との間で戦われました。この攻撃で義仲軍が数百頭の牛の角に松明をくくりつけて敵中に向け放つという奇策を行い、平家軍は、将兵が次々に谷底に転落して壊滅し、平維盛は命からがら京へ逃げ帰ったとされています。
倶利伽羅落(巻第七)
さるほどに源平両方陣を合はす。陣のあはひ、僅か三町ばかりぞ寄せ合はせたる。源氏も進まず、平家も進まず。ややあつて源氏の方より、精兵を選つて、十五騎、楯の面に進ませ、十五騎が上矢の鏑を、ただ一度に平家の陣へぞ射入れたる。平家も十五騎を出だいて、十五の鏑を射返す。源氏三十騎を出だいて、三十の鏑を射さすれば、平家も三十騎を出だいて、三十の鏑を射返さす。源氏五十騎を出だせば、五十騎を出だし、百騎を出だせば、百騎を出だす。両方百騎づつ陣の面に進ませ、互ひに勝負をせんと逸りけるを、源氏の方より制して、わざと勝負をばせさせず。かやうにあひしらひ、日を待ち暮らし、夜に入つて、平家の大勢を、後ろの倶利迦羅谷へ追ひ落さんと謀りけるを、平家これをば夢にも知らず、共にあひしらひ、日を待ち暮らすこそはかなけれ。
さるほどに北南より廻る搦手の勢一万余騎、倶利迦羅の堂の辺に廻り合ひ、箙の方立打ち叩き、鬨をどつとぞ作りける。各後ろを顧み給へば、白旗雲の如くに差し上げたり。「この山は四方巌石であんなれば、搦手よも廻らじとこそ思ひつるに、こはいかに」とぞ騒がれける。さるほどに大手より木曾殿一万余騎、鬨の声を合はせ給ふ。砥浪山の裾、松長の柳原、茱萸の木林に引き隠したりける一万余騎、日宮林に控へたる今井四郎が六千余騎も、同じう鬨の声をぞ合はせける。前後四万騎が喚く声、山も河も、ただ一度に崩るるとこそ聞えけれ。さるほどに次第に暗うはなる、前後より敵は攻め来たる。「汚しや、返せや返せや」と云ふ輩多かりけれども、大勢の傾き立ちたるは、左右なう取つて返す事の難ければ、平家の大勢後ろの倶利迦羅谷へ、我先にとぞ落ち行きける。先に落したる者の見えねば、「この谷の底にも道のあるにこそ」とて、親落せば子も落し、兄が落せば弟も続く、主落せば家子郎等も続きけり。馬には人、人には馬、落ち重なり落ち重なり、さばかり深き谷一つを、平家の勢七万余騎でぞ埋めたりける。巌泉血を流し、死骸丘を成せり。さればこの谷の辺には、矢の穴、刀の瑕残つて、今にありとぞ承る。平家の御方に宗と頼まれたりける上総大夫判官忠綱、飛騨大夫判官景高、河内判官秀国も、、この谷に埋もれて失せにけり。また備中国の住人、瀬尾太郎兼康は、聞ゆる兵にてありけれども、運や尽きにけん、加賀国の住人、蔵光次郎成澄が手にかかつて、生捕にこそせられけれ。また越前国火燧城にて返り忠したりける平泉寺の長吏斎明威儀師も、捕はれて出で来たる。木曾殿、「その法師はあまりに憎きに、まづ斬れ」とて斬らせらる。大将軍維盛通盛、稀有にして加賀国へ引き退く。七万余騎が中より、僅かに二千余騎こそ遁れたれ。
・・・・・・・・
流布本『平家物語』 より |
|
 |
 |
| 倶利伽羅峠の火牛の像 |
倶利伽羅峠の源平供養塔 |
(6) 一ノ谷<兵庫県神戸市須磨区>
言わずと知れた源平の古戦場で、1184年(寿永3)2月に源義経・範頼軍が再挙を計った平氏軍を一ノ谷に襲い、海上に敗走させた戦いで、義経の鵯越の奇襲戦法が知られています。また、須磨海岸の波打ち際での平敦盛と熊谷直実一騎打ちによって打たれた敦盛の話は、『平家物語』中でも最も悲しく哀れを誘う場面として有名です。須磨寺には敦盛愛用の青葉の笛、合戦時に弁慶が安養寺から長刀の先に掛けて担いできて陣鐘の代用にしたという弁慶の鐘などの宝物があります。また、境内には、敦盛の首塚、義経の腰掛け松などの史跡があり、古来から『平家物語』を偲んで文人墨客が訪れている所です。それを示すように松尾芭蕉、正岡子規、与謝蕪村、尾崎放哉などの句碑や歌碑が建てられています。須磨浦公園には、敦盛塚や源平合戦800年記念碑などあって当時の合戦を思い出させてくれます。
敦盛(巻第九)
さるほどに一谷の軍敗れにしかば、武蔵国の住人、熊谷次郎直実、平家の君達助け舟に乗らんとて、汀の方へや落ち行き給ふらん、あつぱれよき大将軍に組まばやと思ひ、渚を指して歩まする処に、ここに鶴縫うたる直垂に、萌黄匂の鎧着て、鍬形打つたる甲の緒を締め、金作の太刀を帯き、二十四差いたる切斑の矢負ひ、滋籐の弓持ち、連銭葦毛なる馬に、金覆輪の鞍置いて乗つたる武者一騎、沖なる舟を目にかけ、海へさつとうち入れ、五六段ばかり泳がせける。熊谷、「あれはいかに、よき大将軍とこそ見参らせ候へ。正なうも敵に後ろを見せ給ふものかな。返させ給へ返させ給へ」と、扇を挙げて招きければ、招かれて取つて返し、渚に打ち上がらんとし給ふ処に、波打際にて押し並び、むずと組んで、どうと落ち、取つて押さへて首を馘かんとて、内甲を押し仰けて見たりければ、年の齢十六七ばかりなるが、薄仮粧して鉄漿黒なり。我が子の小次郎が齢ほどにて、容顔まことに美麗なりければ、何処に刀を立つべしとも覚えず。「いかなる人にて渡らせ給ひやらん。名乗らせ給へ。助け参らせん」と申せば、「汝は誰そ、名乗れ聞かう」「物その者では候はねども、武蔵国の住人熊谷次郎直実」と名乗り申す。「汝が為にはよい敵ぞ。名乗らずとも首を取つて人に問へ。見知らうずるぞ」とぞ宣ひける。熊谷、「あつぱれ大将軍や。この人一人討ち奉りたりとも、負くべき軍に勝つ事はよもあらじ。また助け奉るとも、勝つ軍に負くる事もよもあらじ。我が子の小次郎が薄手負うたるをだに直実は心苦しう思ふぞかし。この殿の父討たれ給ひぬと聞き給ひてさこそは嘆き悲しび給はんずらめ。助け参らせん」とて、後ろを顧みたりければ土肥、梶原五十騎ばかりで出で来たり。熊谷涙をはらはらと流いて、「あれ御覧候へ。いかにもして助け参らせんとは存じ候へども、御方の軍兵雲霞の如くに満ち満ちて、よも遁れ参らせ候はじ。あはれ同じうは直実が手に懸け奉つてこそ、後の御孝養をも仕り候はめ」と申しければ、「ただいかやうにも疾う疾う首を取れ」とぞ宣ひける。熊谷あまりにいとほしくて、何処に刀を立つべしとも覚えず、目も眩れ心も消え果てて、前後不覚に覚えけれども、さてしもあるべき事ならねば、泣く泣く首をぞ馘いてける。「あはれ弓矢取る身ほど口惜しかりける事はなし。武芸の家に生れずば、何しに只今かかる憂き目をば見るべき。情なうも討ち奉つたるものかな」と、袖を顔に押し当て、さめざめとぞ泣き居たる。首を包まんとて、鎧直垂を解いて見ければ、錦の袋に入れられたりける笛をぞ腰に差されたる。「あないとほし、この暁城の内にて、管絃し給ひつるは、この人々にておはしけり。当時御方に東国の勢、何万騎かあるらめども、軍の陣へ笛持つ人はよもあらじ。上臈はなほも優しかりけるものを」とて、これを取つて大将軍の御見参に入れたりければ、見る人涙を流しけり。
・・・・・・・・
流布本『平家物語』 より |
|
 |
 |
| 須磨寺本堂(神戸市須磨区) |
須磨浦公園の敦盛塚(神戸市須磨区) |
(7) 屋島<香川県高松市>
1185年(文治元)2月、屋島に留まっていた平氏軍を源義経らが急襲し、海上に追いやった戦いの場所です。『平家物語』では、那須与一が、源義経の命により、船上の扇の的を射抜いた名場面があります。屋島からは瀬戸内海と古戦場が一望でき、屋島寺などに遺跡や遺品が残されていて、この物語の情景を思い浮かべるには最適の場所です。
那須与一(巻第十一)
・・・・・・・・
判官、「いかに宗高あの扇の真中射て、敵に見物せさせよかし」と宣へば、与一「仕つとも存じ候はず。これを射損ずるほどならば、長き御方の御弓箭の瑕にて候ふべし。一定仕らうずる仁に、仰せ付けらるべうもや候ふらん」と申しければ、判官大きに怒つて、「今度鎌倉を立つて、西国へ赴かんずる者共は、皆義経が命を背くべからず。それに少しも子細を存ぜん殿原は、これより疾う疾う鎌倉へ帰らるべし」とぞ宣ひける。与一重ねて辞せば、悪しかりなんとや思ひけん、「さ候はば、外れんをば知り候ふまじ、御諚で候へば、仕つてこそ見候はめ」とて御前を罷り立ち、黒き馬の太う逞しきに、丸海鞘摺つたる金覆輪の鞍置いてぞ乗つたりける。弓取り直し、手綱掻い繰つて、汀へ向いてぞ歩ませける。御方の兵共、与一が後ろを遥かに見送りて、「一定この若者、仕つつべう存じ候ふ」と申しければ、判官世にも頼もしげにぞ見給ひける。矢比少し遠かりければ、海の面一段ばかりうち入れたりけれども、なほ扇のあはひは、七段ばかりもあるらんとぞ見えし。
比は二月十八日酉の刻ばかりの事なるに、折節北風烈しくて、磯打つ波も高かりけり。舟は揺り上げ揺り据ゑて漂へば、扇も串に定まらず、閃いたり。沖には平家舟を一面に並べて見物す。陸には源氏轡を並べてこれを見る。いづれもいづれも晴れならずといふ事なし。与一目を塞いで、「南無八幡大菩薩、別しては我国の神明、日光権現、宇都宮、那須湯泉大明神、願はくは、あの扇の真中射させて賜ばせ給へ。射損ずるほどならば、弓切り折り自害して、人に二度面を向くべからず。今一度本国へ迎へんと思し召さば、この矢外させ給ふな」と、心の内に祈念して、目を見開いたれば、風少し吹き弱つて、扇も射よげにぞなりにけれ。与一鏑を取つて番ひ、よつ引いてひやうと放つ。小兵といふ条、十二束三伏、弓は強し、鏑は浦響くほどに長鳴りして、過たず扇の要際、一寸ばかり置いて、ひいふつとぞ射切つたる。鏑は海に入りければ、扇は空へぞ揚がりける。春風に一揉み二揉み揉まれて、海へさつとぞ散つたりける。皆紅の扇の、日出だいたるが夕日に輝いて、白波の上に、浮きぬ沈みぬ揺られけるを、沖には平家舷を叩いて感じたり。陸には源氏箙を叩いて、響めきけり。
流布本『平家物語』 より |
|
 |
 |
| 屋島寺(香川県高松市) |
屋島の古戦場(香川県高松市) |
(8) 壇ノ浦<山口県下関市>
1185年(文治元)3月に、平氏軍と源義経を総大将とする源氏軍が戦い、平家滅亡となった最後の一戦が行われた場所です。この時に、幼い安徳天皇は母の平徳子と共に船から海に飛び込みましたが、徳子だけが助けられました。『平家物語』には、“先帝御入水”として、書かれていて、哀惜の情を強く感じる部分なのです。下関市には安徳天皇を祀った赤間神宮があり、この合戦で亡んだ平家一門の墓があります。有名な耳なし芳一の話もここを舞台にしたものです。また、隣接して、安徳天皇阿弥陀寺稜もあり、毎年、5月2日の安徳天皇の命日より3日間に亘って、先帝祭も行われています。
先帝御入水(巻第十一)
・・・・・・・・
主上は今年八歳にぞ成らせおはしませども、御年のほどよりは、遥かにねびさせ給ひて、御容美しう、辺も照り輝くばかりなり。御髪黒う優々として、御背中過ぎさせ給ひけり。あきれたる御有様にて、「抑も我をば何方へ具して行かんとはするぞ」と仰せければ、二位殿、稚き君に向かひ参らせ、涙をはらはらと流いて、「君は未だ知ろし召され候はずや、前世の十善戒行の御力によつて、今万乗の主とは生れさせ給へども、悪縁に引かれて、御運既に尽きさせ候ひぬ。まづ東に向かはせ給ひて、伊勢大神宮に御暇申させおはしまし、その後西に向かはせ給ひて、西方浄土の来迎に預からんと誓はせおはしまし、御念仏候ふべし。この国は粟散辺土とて、心憂き境なれば、極楽浄土とて、めでたき所へ、具し参らせ候ふぞ」と、泣く泣く掻き口説き申されければ、山鳩色の御衣に、鬢結はせ給ひて、御涙に溺れ、小さう美しき御手を合はせて、まづ東に向かはせ給ひて、伊勢大神宮に御暇申させ給ひ、その後西に向かはせ給ひて、御念仏ありしかば、二位殿やがて抱き参らせて、「波の底にも都の候ふぞ」と慰め参らせて、千尋の底にぞ沈み給ふ。悲しきかな、無常の春の風、忽ちに花の御姿を散らし、情無きかな、分段の荒き波、玉体を沈め奉る。殿をばと名付けて、長き栖と定め、門をば不老と号して、老いせぬ扉鎖とは書きたれども、未だ十歳の内にして、底の水屑と成らせおはします。十善帝位の御果報、申すも中々おろかなり。雲上の龍降つて、海底の魚と成り給ふ。大梵高台の閣の上、釈提喜見の宮の内、古は槐門棘路の間に、九族を靡かし、今は舟の内波の下にて、御命を一時に滅ぼし給ふこそ悲しけれ。
流布本『平家物語』 より |
|
 |
 |
| 赤間神宮(山口県下関市) |
平家一門の墓(山口県下関市) |
(9) 寂光院<京都府京都市左京区>
寂光院は、安徳天皇の母である建礼門院平徳子が、平家滅亡後に営んだ草庵でした。『平家物語』の末尾に描かれていて、「盛者必衰の理」の結びとなっています。そこに佇んでいると、まさに諸行無常の鐘の音が聞こえてくるようです。しかし、2000年(平成12)に放火によって、本堂と本尊地蔵菩薩が焼失してしまいました。現在は、本堂が再建されて、再び拝観出来るようになったのです。
大原入(灌頂巻)
・・・・・・・・
文治元年長月の末に、かの寂光院へ入らせおはします。道すがら、四方の梢の色々なるを、御覧じ過ぐさせ給ふほどに、山陰なればにや、日も既に暮れかかりぬ。野寺の鐘の入相の音凄く、分くる草葉の露茂み、いとど御袖濡れ増さり、嵐烈しく、木の葉乱りがはし。空掻き曇り、いつしかうち時雨れつつ、鹿の音幽かに音信れて、虫の恨みも絶々なり。とにかくに取り集めたる御心細さ、譬へやるべき方もなし。浦伝ひ島伝ひせしかども、さすがかくは無かりしものをと、思し召すこそ悲しけれ。岩に苔生して、寂れたる所なれば住ままほしくぞ思し召す。露結ぶ庭の萩原霜枯れて、籬の菊の枯々に移ろふ色を御覧じても、御身の上とや思しけん。仏の御前へ参らせ給ひて、「天子聖霊、成等正覚、頓証菩提」と祈り申させ給ひけり。いつの世にも忘れ難きは、先帝の御面影、ひしと御身に添ひて、いかならん世にも、忘るべしとも思し召さず。さて寂光院の傍らに、方丈なる御庵室を結び、一間をば寝所に定め、一間をば仏所に設ひ、昼夜朝夕の御勤め、長時不断の御念仏、怠る事なくして、月日を送らせ給ひけり。
かくて神無月中の五日の暮れ方に、庭に散り敷く楢の葉を、物踏み鳴らして聞えければ、女院、「世を厭ふ処に、何者の問ひ来るぞ。あれ見よや。忍ぶべき者ならば、急ぎ忍ばん」とて見せらるるに、小鹿の通るにてぞありける。女院、「さていかにや」と仰せければ、大納言典侍殿涙を押さへて、
岩ねふみ誰かはとはん楢の葉のそよぐは鹿のわたるなりけり
女院哀れに思し召して、この歌を窓の小障子に遊ばし留めさせおはします。
かかる御徒然の中にも、思し召し準ふる事共は、辛き中にも数多あり。軒に並べる樹をば、七重宝樹と象れり。岩間に湛ふる水をば、八功徳水と思し召す。無常は春の花、風に随つて散り易く、有涯は秋の月、雲に伴つて隠れ易く、昭陽殿に花を翫びし朝には、風来たつて匂ひを散らし、長秋宮に月を詠ぜし夕べには、雲覆つて光を隠す。昔は玉楼金殿に、錦の褥を敷き、妙なる御住まひなりしかども、今は柴引き結ぶ草の庵、余所の袂も萎れけり。
流布本『平家物語』 より |
|
 |
 |
| 寂光院の門(京都市左京区) |
再建された寂光院本堂(京都市左京区) |
| この作品を読んでみたい方は、簡単に手に入るものとして、現在、『平家物語』が、講談社文庫(上・下)、講談社学術文庫(全12冊)、岩波文庫(全4冊計3,200円)他から出版されています。 |