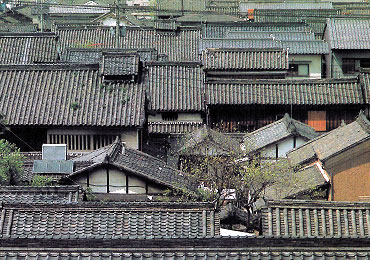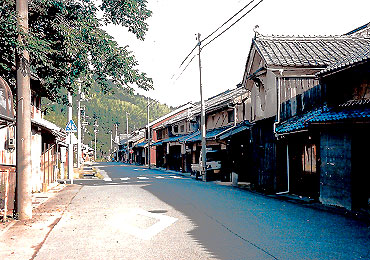|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 町並み関係用語集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【相倉】(あいのくら)富山県南栃市の相倉は、20棟の合掌造り家屋が残る五箇山地域の山村集落です。この形式の民家は、白川郷(岐阜県)から五箇山(富山県)にかけて分布していて、大きな切妻屋根が特徴で、手を合わせた姿をしているのでこの名が付きました。現在残る建物は、江戸時代末期から明治時代末期に建てられたもので、昔は数十人の家族が住んでいて、養蚕をしていたとのことです。1994年(平成6)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。また、1995年(平成7)には、白川郷の荻町、五箇山の菅沼と共に、「白川郷・五箇山の合掌造り集落」として、世界遺産(文化遺産)に登録されたのです。
【赤沢】(あかざわ)山梨県南巨摩郡早川町の赤沢は、身延往還の宿場町として栄えたところで、山の急斜面にへばりつくように民家が並び、長い石畳の道がつづら折りになっています。江戸時代から続く宿場と山村の雰囲気がよく残されているので、1993年(平成5)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。かつては、身延山、七面山登山の講中宿としてにぎわい、その旅籠「江戸屋」が、まだ1軒だけ営業していて泊まることもできます。ここを歩くと気分は参拝に向かう江戸時代の旅人となることができます。
【足助】(あすけ)愛知県豊田市の足助は、飯田街道沿いの商家町・宿場町として栄えたところで、白壁の土蔵や、格子戸、黒い板壁など、昔ながらの建物が並んでいます。この町並みは、江戸時代中期の1775年(安永4)にあった大火後に、防火を意図して塗籠造りの町家が形成されたことを引き継いでいるのです。「妻入り型」や「平入り型」という古くからの家並みが2kmにわたって続き、昔の町並みがよく残されているので、2011年(平成23)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。その中でも、旧紙屋鈴木家(国の重要文化財)、「足助中馬館」(大正時代の銀行で県指定文化財)、莨屋岡本家住宅(市指定有形民俗文化財)、「足助資料館」(大正時代の蚕業取締所)、玉田屋旅館(江戸末期の旅籠で現在も泊まれる)、旧三嶋館、マリリン小路などを巡ってみると、とてもレトロな雰囲気が感じられます。
【有松】(ありまつ)愛知県名古屋市緑区の有松は、東海道沿いの有松絞の染織町として栄えたところで、昔ながらの建物が並んでいます。これは、江戸時代後期の1784年(天明4)にあった火災後に、防火を意識して、瓦葺、塗籠造りで、“うだつ”のある、町並みが形成されたものです。昔の町並みがよく残されているので、1984年(昭和59)には名古屋市の「有松町並み保存地区」に指定され、2016年(平成28)には、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。その中でも、服部家住宅(県指定有形文化財)、岡家住宅(市指定有形文化財)、小塚家住宅(市指定有形文化財)、竹田家住宅(市指定有形文化財)、棚橋家住宅(国登録文化財)、中濵家住宅(国登録文化財)、「有松・鳴海絞会館」などを巡ってみると、有松絞のこともわかり、昔ながらの雰囲気も感じられます。
【出石】(いずし)兵庫県豊岡市の出石は、江戸時代は、出石藩(小出氏→松平氏→仙谷氏)の城下町として発展しました。現在でも、城下町の町並みが良く残されていて、小京都の一つとして人気があり、1987年(昭和62)に最初の兵庫県指定景観形成地区に指定され、2007年(平成19)には、国の重要伝統的建造物群保存地区にも選定されました。江戸時代から発展してきた城下町は、1876年(明治9)に起こった大火によって、家屋966、社寺39、土蔵290が焼き尽くされてしまいました。その後、建築された明治時代の寺院や町家、および焼失を免れた武家屋敷や社寺が現存していて、歴史的町並みを今日に伝えているのです。町並みの中にある出石家老屋敷、伊藤清永美術館、辰鼓楼、出石史料館、明治館、永楽館などを巡って、出石城跡へと登ってみると、落ち着いた風情のある城下町が見渡せるので、お勧めコースです。また、名物皿そばを食べてみるのも良いと思います。
【出水麓】(いずみふもと)鹿児島県出水市の出水麓は、江戸時代薩摩藩の麓集落の一つで、出水郷に赴任する薩摩藩士の住宅兼陣地として、起伏の多い丘を整地し、道路を掘り、川石で石垣を築いて作られたと言われています。その整地には、1599年(慶長4)から約30年かかりました。今でも、建設当初の面影を残す街路、その両側に築かれた石垣や生垣、武家門と武家屋敷や庭園などの古い町並みがよく残されています。その中で、1976年(昭和51)に、武家屋敷の所有者で構成された「出水麓武家屋敷保存会」が組織されて、保存活動に取り組むようになり、1995年(平成7)には、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。現在は、公開武家屋敷税所邸、公開武家屋敷竹添邸、公開武家屋敷武宮邸、御仮屋門、宮路邸(篤姫ロケ地)、三原邸などを見て回ることができ、美しい街路景観を堪能できます。
【伊根】(いね)京都府与謝郡伊根町の伊根浦には、船の収納庫の上に住居を備えた、伝統的建造物(船屋)が、湾に向かって、びっしりと並んでいて、特異な景観を作り出しているので、2005年(平成17)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。海は、ライトブルーに輝き、とてもすばらしい眺めで、こういう自然の中に息づいている人々の暮らしは、大変希少なものに思われます。観光船に乗って、海側から眺めることも可能で、船は湾内を周航し、海上から船屋集落を見させてくれます。それが、澄んだ海とマッチしてなんとも言えないような光景を作り出していて、なかなかのものです。また、「男はつらいよ」シリーズの映画の中でここを舞台に虎さんが活躍したのがありました。船屋民家が民宿として営業しているところで、とても風情があります。しかし、こういう漁村は家が建て込んでいて、道も細く曲がりくねっていて、車で巡るのは適していないので、駐車場に車を置いて徒歩で巡ることをお勧めします。
【今井町】(いまいまち)奈良盆地の中央部の奈良県橿原市にあり、戦国時代の寺内町が原型となり、今も江戸時代以前の建物が多数存在しています。環壕が周囲を取り囲み、その中に入ると何百年も続いて来た古い商家の町並みが残されています。昔からの自治集落の伝統が今に伝えられていてとても貴重です。近世以前の町並みがこれだけまとまって残っている場所は日本では他に無いといわれ、1993年(平成5)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。その中には、今西家住宅、豊田家住宅、上田家住宅、音村家住宅などの国指定重要文化財の建物が数多くあり、とてもみごとなものです。
【岩村町本通り】(いわむらまちほんどおり)岐阜県恵那市にあり、江戸時代の岩村城(日本三大山城の一つ)の城下町として発展しました。江戸時代前期に岩村城主となった大給松平氏によって町並みの原型が形成され、その後も岩村藩三万石の城下町として繁栄したのです。南北に縦長の敷地割りで、家屋は切妻造りの平入りで、格子、出格子、桟瓦葺きがよく見られ、なまこ壁や武者窓が見られるところもありました。昔からの町並みがよく残されていて貴重なので、1998年(平成10)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されたのです。中でも、木村邸(市指定有形文化財)、勝川家、柴田家(いわむら美術の館)、土佐屋、上町まちなか交流館などを巡ってみると昔ながらの雰囲気が伝わってきます。
【宇陀松山】(うだまつやま)奈良県宇陀市の松山は、戦国時代に国人領主秋山氏により築かれた秋山城の城下町を起源とし、江戸時代前期は宇陀松山藩の陣屋町として栄えました。1694年(元禄7)からは江戸幕府の天領となり、商業地として栄え、明治維新以降も、郡役所や裁判所がおかれるなど宇陀地域の中心として発展します。木材と特産の吉野葛の集散地ともなり、商家も多く、昭和時代中頃まで賑わいました。近世初頭の敷地割と江戸時代から明治時代の商家が数多く残る中心街は、現在もその風情を残しており、2006年(平成18)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。その中でも、薬草園の森野旧薬園(国史跡)、松山西口関門(国の史跡)、山邊邸(県重要文化財)、薬の館(市指定文化財)などを巡ってみると、とてもレトロな雰囲気が感じられます。
【内子】(うちこ)愛媛県喜多郡内子町にあり、江戸時代後期から明治時代にかけて木蝋の生産によって栄えた町です。その面影が今も色濃く残っているのが、八日市・護国地区の町並みで、約600mの通りに伝統的な造りの町家や豪商の屋敷が、当時のまま軒を連ねていて、1982年(昭和57)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。中でも「上芳我邸」は、かつては代々木蝋を生産していた家で、はぜの実から木蝋を生産する過程を興味深く学ぶことができます。街並みの中ほどにある、「商いとくらし博物館」は、江戸後期から明治期の商家をそのまま利用し、1921年(大正10)年頃の商家(薬屋)の暮らしを人形と当時の道具類を使って再現しており、とても面白く見て回れますし、内子町の歴史や民俗、郷土の生んだ人物について、模型、映像などを用いて説明していて勉強になるのです。また、「内子座」は、昔ながらの芝居小屋が現存し、今でも時々公演が行われているとのことで、とても興味深かったのです。この町並みはその他にも、本芳我家、大村家、大森和蝋燭屋、高橋邸など見所も多く、レトロな雰囲気に浸りながら、散策することができます。
【海野宿】(うんのじゅく)長野県東御市にあり、1625年(寛永2)に、脇往還である北国街道の宿場として、江戸幕府によって設置され、江戸時代前期から明治時代にかけて、宿場と養蚕によって栄えた町です。約 650 mにわたって町並みが続き、本陣1軒と脇本陣2軒、伝馬屋敷59軒、旅籠23軒があり、佐渡金山への輸送、北陸諸藩からの大名行列、善光寺参拝客などで繁盛したのです。明治時代以降、街道の往来が減少すると養蚕業も営んでいました。現在でも、昔の宿場町がよく保存されていて、それは、みごとな家並みで、1987年(昭和62)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。道の真ん中に水路が流れていて、昔の街道の風情をよく残し、海野宿資料館、なつかしの玩具展示館、土産物屋、飲食店などもあるので、徒歩でのんびり散策するのに向いています。
【大内宿】(おおうちじゅく)福島県南会津郡下郷町にあり、脇往還である会津西街道(会津若松~日光今市)の会津城下から3番目の宿場町で、江戸時代前期の1640年(寛永17)頃に整備されました。大内峠(標高900m)の南の山間にあり、寄棟造りの茅葺き民家が道路と直角に整然と並べられていて、見事な景観をなしています。1981年(昭和56)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されて、全国的に脚光を浴びることになりました。現在でも、生活をしている民家がほとんどで、民宿や食堂、土産物屋などをやっているところも多くあります。大内宿本陣跡には、茅葺きで復元された「下郷町町並み展示館」があって、宿場の歴史を学ぶことができますし、名物の蕎麦を食べたり、民宿に泊まったりして、江戸時代にタイムスリップしたようなレトロな雰囲気を体験するのも良いと思います。
【大森銀山】(おおもりぎんざん)島根県大田市の大森銀山(石見銀山)は、戦国時代後期から江戸時代前期にかけて最盛期を迎えた日本最大の銀山でした。しかし、銀の産出量は減少し、明治期以降は枯渇した銀に代わり、銅などが採鉱されましたが、昭和時代前期には、完全に閉山するに至ったのです。その後も銀山に関わる施設跡や町並みが残され、武家屋敷、商家、寺社などが往時の姿を留めているので。1967年(昭和42)に石見銀山は「大森銀山遺跡」として県指定史跡に指定され、さらに1969年(昭和44)には国から「石見銀山遺跡」として史跡に指定されたのです。さらに、1987年(昭和62)には、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。また、2007年(平成19)には、温泉津と共に、「石見銀山遺跡とその文化的景観」として、世界遺産(文化遺産)に登録されたのです。中でも、石見銀山世界遺産センター(石見銀山関連の展示あり)、大久保間歩(ツアー形式により限定的に坑道を公開)、龍源寺間歩(観光坑道として常時公開)、代官所跡 (石見銀山資料館)、熊谷家住宅 (国の重要文化財)、旧河島家、渡辺家住宅、羅漢寺五百羅漢などを巡ってみると、当時の銀山の様子とその繁栄ぶりがわかって勉強になりました。
【荻町】(おぎまち)岐阜県大野郡白川村の荻町は、59棟の合掌造り家屋が残る白川郷の山村集落です。この形式の民家は、白川郷(岐阜県)から五箇山(富山県)にかけて分布していて、大きな切妻屋根が特徴で、手を合わせた姿をしているのでこの名が付きました。現在残る建物は、江戸時代末期から明治時代末期に建てられたもので、昔は数十人の家族が住んでいて、養蚕をしていたとのことです。1976年(昭和51)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。また、1995年(平成7)には、五箇山の相倉、菅沼と共に、「白川郷・五箇山の合掌造り集落」として、世界遺産(文化遺産)に登録されたのです。中でも、和田家(国の重要文化財)、長瀬家、神田家、明善寺庫裡郷土館、白川郷 田島家養蚕展示館、野外博物館 合掌造り民家園、荻町城跡展望台などを巡ってみると合掌造りとその生活についていろいろ学ぶことができます。
【加賀橋立】(かがはしだて)石川県加賀市にある橋立は、江戸後期から明治中期にかけて活躍した北前船の船主や船頭が多く居住した集落です。今でも、その町並みが良く残されているので、2005年(平成17)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。保存地区は、東西約680m、南北約550m、面積約11.0haの範囲で、赤瓦屋根の立派な家をよく見かけ、敷石や石垣には淡緑青色の笏谷石が使われ、主屋のまわりに土蔵や付属屋、庭園などを配しています。明治から大正時代には、「日本一の富豪村」と称されていたとのことで、その名残が伺えました。中でも「北前船の里資料館」、「蔵六園」(登録有形文化財)、「忠谷家住宅」(国指定重要文化財)などが見所です。
【角館】(かくのだて)秋田県仙北市にある角館は、みちのくの小京都と呼ばれるところです。江戸時代に秋田藩の支藩がおかれたところで、武家屋敷が残り、城下町の風情が色濃く残っていて、1976年(昭和51)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。武家屋敷通り沿いには、古い武家屋敷が並び、黒板塀や茅葺き屋根などに情緒があり、石黒家(市指定史跡)、青柳家(県指定史跡)、松本家(県指定有形文化財)、岩橋家(県指定史跡)、河原田家(市指定史跡)、小田野家(市指定史跡)などが並んでいます。春には、古木のしだれ桜が満開となり、すばらしい桜のトンネルが出現し、とても情緒があるのです。
【笠島】(かさしま)香川県丸亀市塩飽本島町にある笠島は、以前は塩飽水軍、塩飽廻船の根拠地としてもっとも栄えた港町でした。今でも、その町並みが良く残されているので、1985年(昭和60)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。町並みは、江戸時代の建物が13棟、明治時代の建物が20棟ほど残っています。廻船問屋など豪商の屋敷や町屋などから成り、正面を格子構えとし、2階に虫籠窓を開けた町屋形式の家が密集して建っているのです。その内、3軒の屋敷が一般に公開され見学することができ、とても静かなところなのでゆっくりと散策して回れます。少し離れて、史跡塩飽勤番所があります。
【川越】(かわごえ)埼玉県中南部の川越市にあり、江戸時代は、江戸城の北方の守りの要として、川越城があって、歴代の城主は譜代の重臣が配されていました。江戸との間には、川越街道や新河岸川の舟運が通っていて、市が開かれ、商業も発達して、城下町も発達し、“小江戸”とも称されていたのです。しかし、1893年(明治26)の大火によって、大打撃を受けたものの、火災に強い蔵造によって復興し、今日の蔵造の町並みを形成することになります。現在でも、30数棟の蔵造りの商家が軒を連ねていて、1992年(平成4)に電柱・電線の地中埋設工事が完了し、1999年(平成11)に、重要伝統的建造物群保存地区に指定されました。また、2007年(平成19)には「美しい日本の歴史的風土100選」にも選定されています。町並みの中心にある一番街には、大沢家住宅(国の重要文化財)、時の鐘、「蔵造り資料館」、「山崎美術館」、「服部民俗資料館」、「蘭山記念美術館」、「松下紀久雄むかし絵美術館」、「川越まつり会館」などがあって、巡ってみるとレトロな気分になれると共に、蔵造りについて学ぶこともできます。また、周辺には江戸時代前期の文化財が豊富な「喜多院」、江戸時代後期の川越城本丸御殿も残り、「川越市立博物館」や「川越市立美術館」、菓子屋横丁などもあって、町並み散策が楽しくできるところです。
【木曽平沢】(きそひらさわ)長野県塩尻市(旧楢川村)にあり、安土桃山時代の1598年(慶長3)に奈良井川左岸の道が反対側(右岸)に付け替えられたことをきっかけに、周辺山林に依拠して生活していた人達が、新しい道沿いに住むようになって、集落が造られていったと考えられています。江戸時代前期に、その道が中山道として整備されていくと、奈良井宿の枝郷として、檜物細工や漆器等を生産することで生計を立てるようになっていきました。江戸時代後期になると、それらの漆器は「平沢塗物」の名で流通するようになり、日本有数の漆器生産地となっていったのです。現在でも、本通りには漆器店が立ち並び、金西町では漆器職人の住居が続いていて、全体として漆工町と呼ばれる独特の町並み景観を形成していて、とても貴重なので、2006年(平成18)に、重要伝統的建造物群保存地区に指定されました。約12.5haの保存地区内に建築物201件、工作物20件、環境物件16件があり、漆塗の作業場である塗蔵が立ち並んでいるのが特徴で、町並みを巡りながら、数十軒ある漆器店に立ち寄って買い物をしたり、近くにある「木曽漆器館」(有形民俗文化財木曽漆器の製作工程はじめ、作品や資料を展示)を見学することも可能です。
【吉良川】(きらがわ)高知県室戸市吉良川町にあり、明治期に建てられた土佐漆喰を使った白壁の商家、台風等の暴風雨から町屋を守るためにっけられた水切り瓦の蔵や河原石や浜石でつくられた石垣塀”いしぐろ”などがあって、独特の景観を成しています。この町は、良質な木炭と薪が取れることから「土佐備長炭」の積み出し港として、明治時代から昭和時代前期にかけて繁栄し、今の町並みが形成されたのです。在郷町として日本の懐かしい町並みを今に残し、とても貴重なので、1997年(平成9)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。伝統的建造物が120棟もあり、これらを巡ってみると、明治・大正期へタイムスリップしたような感じとなります。
【熊川宿】(くまがわじゅく)福井県三方上中郡若狭町にあり、脇往還である鯖街道(若狭~京都)の宿場町です。安土桃山時代の1589年(天正17)に小浜城主浅野長政によって整備され、江戸時代には、街道随一の賑わいでした。今でも旧街道に沿って前川という水量豊かな水路が流れ、真壁造または塗籠造の伝統的建築物が多数残り、よく昔の景観を残しているので、1996年(平成8)に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。現在でも、古い建物を利用して、資料館、食事処、喫茶店、雑貨店などをやっているところも結構あります。中でも、若狭鯖街道熊川宿資料館宿場館(旧熊川村役場)、松木神社・義民館(義民松木庄左衛門を祀る)、旧問屋倉見屋(国指定重要文化財)、菱屋(勢馬清兵衛家)、旧逸見勘兵衛家住宅(町指定文化財)、熊川番所、道の駅若狭熊川宿(熊川宿展示館あり)などを巡ると、レトロな気分になりながら、宿場の歴史を学ぶことができます。
【倉敷川畔】(くらしきがわはん)岡山県倉敷市の倉敷川沿いにある美観地区と呼ばれているところです。江戸時代前期の1642年(嘉永19)に、江戸幕府の天領と定められ、ここに代官所が設置されたことから、蔵屋敷や商家も集中し、備中国の政治・経済の中心地となりました。現在でも、河畔に白壁造りの屋敷や蔵が並び、天領時代の町並みをよく残していてとても貴重なので、1969年(昭和44)に倉敷市の条例に基づき美観地区に定められ、1979年(昭和54)には、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されたのです。中でも倉敷川沿いに、旧大原家住宅(国の重要文化財)、井上家住宅(国の重要文化財)、楠戸家住宅(登録有形文化財)、倉敷館(登録有形文化財)、有隣荘(大原家別邸)、倉敷考古館、 日本郷土玩具館、倉敷民芸館、倉敷物語館などを巡ってみるととてもレトロで情緒ある雰囲気が感じられます。また、隣接する「大原美術館」、「倉敷アイビースクエアー」(倉敷紡績旧工場・近代化産業遺産)などにも行ってみることをお勧めします。
【黒石市中町】(くろいししなかまち)青森県黒石市にあり、江戸時代前期の1656年(明暦2)に、津軽信英が弘前藩から5,000石を分知され、黒石初代領主となり、陣屋を造るとともに新しい町割りを行ったのが基本になっています。 中町や前町は、こみせ(通りに面した町家の正面に設けられたひさし)のある商店が立ち並び商業の中心として栄えました。江戸時代に形成され確立したこみせ通りは、最盛期には総延長4.8kmにも及んでいましたが、明治以降、次第に姿を消していったのです。それでも、中町周辺だけは残されていてとても貴重なので、2005年(平成17)に、3.1haの区域が国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。 中でも、高橋家住宅(国の重要文化財)、鳴海醸造店(市指定文化財)、 中村亀吉酒造店、西谷家住宅、盛家住宅、真土家住宅、私設資料館、津軽黒石こみせ駅などの古い民家を巡ってみるとレトロな造りに感動します。尚、1987年(昭和62)8月10日に、「日本の道100選」にも選定されました。
【五條新町】(ごじょうしんまち)奈良県五條市にあり、江戸時代前期の1608年(慶長13)松倉重政が城下町として建設したのが始まりで、新町通りが紀州街道(伊勢街道)の一部であったことから、商家町、宿場町として発展しました。現在でも、当地区内の建造物330棟のうち143棟が伝統的建築物として特定され、とても貴重なので、2010年(平成22)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。 中でも、栗山家住宅(国の重要文化財)、中邸(県指定文化財)、 栗山邸(市指定文化財)、 まちや館 (木村篤太郎の生家)、まちなみ伝承館、史跡公園長屋門、民俗資料館、古民家レストラン「五條源兵衛」、一ツ橋餅店などの古い民家を巡ってみるとレトロな造りに感動します。
【佐原】(さわら)千葉県香取市にある佐原は、水運を利用して栄えた商家町で、小野川沿いには、古い町並みがよく残され、1996年(平成8)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。小野川沿いや香取街道沿いにには、伊能忠敬旧宅(寛政5年(1793)建築・国指定史跡)のほか、県指定文化財も8件(13棟)が軒をつらねていて、散策するのにもうってつけです。ここで生まれた伊能忠敬は、江戸時代後期に、50歳から学問に志し、測量学を学んで、日本全国の沿岸を実測し、「大日本沿海與地全図」を作成しました。小野川沿いには、旧居が残され、その近くに、「伊能忠敬記念館」もあって、その偉大な足跡をたどれます。
【重要伝統的建造物群保存地区】(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)城下町、宿場町、港町、農漁村集落など伝統的建造物群およびこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、市町村が都市計画区域内では都市計画によって、都市計画以外の区域では、条例によって定める「伝統的建造物群保存地区」のうち、当該市町村の申出にもとづき、その保存地区の全部または一部で我が国にとって、その価値が特に高いものとして、「文化財保護法」に基づき、文部科学大臣が選定した地区のことです。1975年(昭和50)に、「文化財保護法」が改正され、同法第1章総則のなかで文化財の定義を定めた第2条に、新たに「周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの」を「伝統的建造物群」と名づけて文化財の一種に位置づけました。さらに、「伝統的建造物群保存地区」に関する規定をまとめて第5章の2とし、伝統的建造物群およびこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため「伝統的建造物群保存地区」として、市町村が地域地区として都市計画もしくは条例で定めることとします。その中で、第144条の規定に基づき、国(文部科学大臣)は市町村からの申し出を受けて、国にとって価値が高いと判断したものを「重要伝統的建造物群保存地区」に選定し、修理や防災などに対する補助や税制優遇などの支援を行うことになりました。それを受けて、1976年(昭和51)7月23日に文化財保護審議会が初めて7ヶ所(角館町武家屋敷・南木曽町妻蘢宿・白川村荻町・京都市祇園新橋・京都市産寧坂・萩市堀内地区・萩市平安古地区)を重要伝統的建造物群保存地区とする答申を出し、同年9月4日付で選定されます。その後、1980年(昭和55)末には12市町村の15地区、1990年(平成2)末には24市町村の29地区、2000年(平成12)末には84市町村の102地区へと増加しました。さらに、2018年(平成30)末現在では、43道府県98市町村の118地区(合計面積約3,924.9ha)あり、約28,000件の伝統的建造物及び環境物件が特定され保護されています。 【宿根木】(しゅくねぎ)新潟県佐渡市にあり、江戸時代から明治時代まで、日本海航路の千石船寄港地となっていて、たいへん栄えました。現在でも、伝統的建造物は106棟にのぼり、そのほとんどが船大工たちによる板張りで作られた外壁を持つ2階建ての家屋です。とても貴重な町並みなので、1991年(平成3)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。町並み保存地区へ足を踏み入れてみると、まるで時間が止まったようなレトロな建物空間があって驚きます。その中で、公開されている「清九郎」「金子屋」では内部も見学できますが、往時の繁栄を伺わせる立派な建物で、感心させられます。また、近くにある「佐渡国小木民俗博物館」は、廃校になった木造校舎を利用したもので、とても懐かしい感じのする建物です。それに併設して、千石船展示館がありますが、1858年(安政5)に宿根木で建造された「幸栄丸」を実物大に復元し、「白山丸」として展示してあります。民俗資料館の方は、3万点余りの民俗資料が所狭しと展示されていて勉強になります。
【小京都】(しょうきょうと) 昔ながらの町並みや風情が京都に類似していることから、各地の小都市に名づけられた愛称です。室町時代頃から、各地に勢力を張った大名が、京都を真似た町並みの城下町を造り、それが小京都の始まりとなりました。多くは山に囲まれていて、寺社仏閣や町並みに風情があり、地域の中央を趣のある川が流れている所が見られます。現在は、小京都と呼ばれる地域が集まる団体として、昭和時代後期の1985年(昭和60)に結成された、「全国京都会議」があり、1988年(昭和63)の第4回総会で加盟基準が、次のように定められました。により、 【白峰】(しらみね)石川県白山市にあり、手取川西岸の細長い河岸段丘上に形成された、山村・養蚕集落です。周囲を山々に囲まれた豪雪地帯で、稲作はほとんど行われず、江戸時代中期から先進的な養蚕が行われていました。敷地が限定されているため、主屋が通りに面して建ち並ぶ特徴ある街路景観を成し、中央部には、社寺や大家が居を構えています。これらを石垣が囲み、特徴ある景観を造り出し、とても貴重な町並みなので、2012年(平成24)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。主屋は切妻造りで、二階建から三階建、上層階は養蚕に使用されていました。また、豪雪地帯のため、雪下ろし用の大梯子が常設されているのも特徴です。山村ですが、密集して建物があって、町場のような景観を形成しているので、散策するには好都合で、独特の景観を感じることができました。
【関宿】(せきじゅく)三重県亀山市関宿にあり、五街道の一つ、東海道の江戸・日本橋から数えて47番目の宿場でした。東の追分からは伊勢別街道、西の追分からは大和街道が分岐する交通の要衝として、以前は栄えたのです。その昔ながらの風景が残っていて、江戸時代の街道や宿場の雰囲気に感動するのです。東海道では一番往時の町並みを色濃く残していることから、1984年(昭和59)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。町並みの中には、関まちなみ資料館(江戸末期の町家を公開)、旅籠玉屋歴史資料館(旅籠建築を公開)、鶴屋脇本陣(波田野家)、川北本陣跡、百六里庭、伊藤本陣跡、深川屋(銘菓「関の戸」販売)、地蔵院(鐘楼が国の重要文化財)、伊勢鳥居、道標などがあって、江戸時代の街道の様子を知りながら散策することができます。
【全国伝統的建造物群保存地区協議会】(ぜんこくでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちくきょうぎかい)昭和時代後期の1975年(昭和50)の「文化財保護法」の改正により、「伝統的建造物群保存地区」制度が創設され、1979年(昭和54)7月1日に、伝統的建造物群保存地区(伝建地区)を有する13市町村が集い、伝建地区の保存整備に関する調査・研究、情報の収集及び発信等を目的とし発足した協議会です。保存地区の歴史的町並を保存するためのさまざまな情報を収集・蓄積し、これらを会員相互で共有するとともに全国に発信するため、歴史的町並の保存に関わる講演会の開催や、協議会のインターネットホームページの開設などを行ってきました。2025年(令和7)現在では、全国129伝建地区の106自治体によって構成される大きな組織となっています。 【竹富島】(たけとみじま)沖縄県八重山郡竹富町にある竹富島は、日本の最南端に近い、隆起珊瑚礁の小島です。島の中央部に集落がかたまってあり、石灰岩の石垣でほぼ四角に囲われた中に、寄棟造の平屋建てで、独特の赤瓦をのせた民家があります。島の農村集落の古い町並みがよく残されているので、1987年(昭和62)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。島内は水牛車に乗ってゆっくりと散策できます。海はどこまでも澄んでいて、とてもすばらしいのです。
【竹原】(たけはら)広島県竹原市にある竹原地区は、江戸時代後期に製塩そして酒造業で栄えたお屋敷や由緒あるお寺と町並みが今もそのまま残され、“安芸の小京都” と呼ばれています。江戸時代から明治・大正・昭和にかけての妻入り、平入り、長屋型、高塀をもつ屋敷型など多種多様な建造物が立ち並び、古い町並みがよく残されているので、1982年(昭和57)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。また、2000年(平成12)に国土交通省によって、町並地区が「都市景観100選」にも選定されたのです。中でも、「春風館」頼家住宅 「復古館」頼家住宅(国の重要文化財)、頼惟清旧宅(県史跡)、森川邸(市重要文化財)、松阪邸、旧笠井邸、「竹原市歴史民俗資料館」(昭和初期の洋風剣突)などを巡ってみると落ち着いた静けさと時代を超えた雰囲気を感じられると思います。
【知覧】(ちらん)鹿児島県南九州市にある知覧は、江戸時代薩摩藩の麓集落の一つで、今でも、武家屋敷や日本庭園などの古い町並みがよく残されているので、1981年(昭和56)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。通りに沿って連なる石垣と大刈り込みの生垣に当時の面影が感じられ、武家屋敷の庭園は、母ヶ岳(標高517m)を借景として1700年代から1800年代初めに作られたと考えられ、7つの庭園が国の名勝に指定されています。また、太平洋戦争末期に、神風特攻隊が飛び立っていった飛行場のあったところで、「特攻平和祈念館」には、特攻隊員の遺品や遺影が飾られていました。祈念館の隣に特攻隊員が最後を過ごした三角兵舎が復元されていましたが、とてもお粗末な建物で、非常に驚きました。
【妻籠宿】(つまごしゅく)長野県木曽郡南木曽町にあり、五街道の一つ、中山道の江戸・日本橋から数えて42番目の宿場でした。その昔ながらの風景に感動するのですが、これほど、江戸時代の街道や宿場の雰囲気がそのまま残されているところは他にありません。復元されたものも含めて、本陣、脇本陣、問屋場、旅籠、茶屋、高札場、石畳、道標などの昔の街道の要素をすべて見られ、大変貴重な町並みなので、1976年(昭和51)に、最初の国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。江戸時代の街道について知るにはうってつけのところで、歴史の雰囲気を強く感じ取れるのです。
【津和野】(つわの)島根県鹿足郡津和野町にあり、江戸時代は、津和野藩亀井氏4万3千石の城下町として発展しました。現在でも、城下町の町並みが良く残されていて、小京都の一つとして人気があり、2013年(平成25)に、国の重要伝統的建造物群保存地区にも選定されました。中でも、「民俗資料館」は、津和野藩の藩校「養老館」の跡で、長屋門の前の水路にいろとりどりの鯉が泳いでいることで知られています。この、藩校からは小藩ながら多くの有能な人材が輩出しています。その中でも、有名なのは森鴎外と西周で、町内には旧居や記念館があり見学できます。また、「町立郷土館」も、古い建物ですが、結構豊富な展示がしてあり、あの坂崎出羽守と津和野との関係、戊辰戦争における津和野藩の役割など興味深いものが見られます。森鴎外旧宅は、江戸時代は堀端の武家屋敷であったとのことですが、木造平屋建ての簡素な建物で、その裏に立派な「森鴎外記念館」が建てられていました。それ以外にも、西周旧居、津和野今昔館、高砂酒蔵資料館、資料室はぜくら、杜塾美術館などがあって、楽しみながら見て回ることができます。
【奈良井宿】(ならいじゅく)長野県塩尻市奈良井にあり、五街道の一つ、中山道の江戸・日本橋から数えて34番目の宿場でした。その昔ながらの風景に感動するのですが、江戸時代の街道や宿場の雰囲気がとても良く残されているのです。大変貴重な町並みなので、1978年(昭和53)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。町並みの中には、上問屋資料館、旅籠えちごや、高札場、元櫛問屋中村邸、水場、楢川歴史民俗資料館、道標などがあって、江戸時代の街道の様子を学ぶことができます。また、次の藪原宿までの鳥居峠(標高1,197m)越えの道(約8km)は、江戸時代以来の旧中山道を信濃路自然歩道として整備されていて、3時間半ほどで歩いて行くことも可能です。
【吹屋】(ふきや)岡山県高梁市にあり、江戸時代前期から銅山の町として栄え、特に江戸時代後期からはベンガラの生産で栄えたところです。ベンガラとは酸化第二鉄のことで木造建築の赤色顔料として使います。ベンガラ商人たちは、大きな富を蓄え、吹屋往来沿道には、ベンガラ窯元の商家が連なる独特の町並みが出来たのです。ベンガラの混じった赤い壁の商家が続く町並みは独特の景観を作りだしていて、とても貴重なので、1977年(昭和52)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。町並みの中にある旧片山家住宅、郷土館、旧吹屋小学校は公開されていて見学もできるので、それらを見ながら町並みをのんびりと散策するのがお勧めです。また、少し離れていますが、広兼邸、笹畝坑道、ベンガラ館なども巡ってみると一層良いと思います。
【古市・金屋】(ふるいち・かなや)山口県柳井市にあり、江戸時代には岩国藩のお納戸と呼ばれ、商都として賑わったところです。現在でも、往時の面影を残す白壁の町並みや細い路地があって、とても貴重なので、1984年(昭和59)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。その中で、公開されている古い商家の「むろやの園」は、奥行きの長い造りで昔ながらの商家のたたずまいを残し、蔵がいくつもありますが、その中が展示室となっていて、この屋の商いがわかるようになっています。昔は油問屋をしていたようで、裏口は柳井川に通じていて、荷の上げ下ろしをしたとあります。そこを出て古い街並みを歩いていくと、左側に、国指定重要文化財「国森家住宅」があり、中を見学させてもらうと、係りの女性がていねいに説明してくれましたが、その構造がよくわかり、いろいろな工夫がされていることに驚きました。隠し階段や二階から荷を降ろすための滑車、防火のためのシステムなど昔の人の知恵に感心させられたのです。それ以外にも、柳井市町並み資料館・松島詩子記念館、甘露醤油資料館、湘江庵などを巡ってみるのがお勧めです。
【前沢】(まえさわ)福島県南会津郡南会津町の前沢集落には、茅葺きの曲屋などが10数棟残され、美しい集落を形成していて、1988年(昭和63)に、舘岩村環境美化条例に基づく保存地区に指定され、2011年(平成23)に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されて、さらに保存処置が講じられるようになりました。この集落は、文禄年間(1592~1595年)に横田城主・山内氏勝の家臣、小勝入道沢西が、主家滅亡後、この地に移り住んだことに始まると伝えられています。しかし、1907年(明治40)の大火によって、全戸焼失し、各戸が同一の大工集団により一時期に建築されので、整った統一的景観を保っているといいます。舘岩川を渡って集落へ入っていくと手前に水車小屋がありその向こうに花しょうぶ園が広がっています。渓流沿いに、色とりどりの花々も咲いていて、昔懐かしい山里風景です。この辺では、L字形をした民家を曲家(まがりや)と称し、飛び出した部分が厩(うまや)になっている中門造りで、農耕馬が家族の一員のように飼われていたとのことです。この形式の民家は、東北の南部地方にも見られますが、この地域の特徴点は、出入口が2ケ所あることと、出っ張り部が切妻屋根になっている点だといいます。前沢集落内の舘岩村曲家資料館では、内部が公開されていて、村の古老とおぼしき人が、囲炉裏端でいろいろと説明してくれました。昔ながらの生活様式が再現されていて、当時の暮らしぶりを知ることができます。
【町並み保存センター】(まちなみほぞんせんたー)伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物の空き家などを利用して郷土資料等の展示機能や案内・交流などの機能を持たせた施設です。このセンターの管理・運営には地区住民が参画し、伝統的建造物としての公開や町並保存に関わるイベントの会場、来訪者との交流会場などとして積極的に活用されている場合もあります。 【豆田町】(まめだまち)大分県日田市にある花月川沿いの商家町です。江戸時代前期の1639年(寛永16)に、幕府の直轄地になって、日田代官所が置かれ、御用達商人が集中していたのが豆田町でした。 今でも、江戸時代前期から昭和前期の商家や土蔵が多く残り、古い町並みが残されていて、とても貴重なので、2004年(平成16)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。南北2本の通りと東西5本の通りによる整然とした町割を残し、各時代で特色ある多様な建築様式は、変化に富んだ町並を形成し、伝統的建築物166件、伝統的工作物84件があり、“九州の小京都”とも言われています。その中でも、草野家住宅(国指定重要文化財)、長福寺本堂(国指定重要文化財)、岩尾家住宅(登録有形文化財)、廣瀬淡窓旧宅、「天領日田資料館」、「豆田まちづくり歴史交流館」などの古い家々を巡ってみるととてもレトロな気分になれました。また、少し離れますが、廣瀬淡窓が江戸時代後期に開いた私塾「咸宜園」(国指定史跡)に立ち寄ってみるのも良いかと思います。
【美々津】(みみつ)宮崎県日向市にある耳川河口の港町で、江戸時代は高鍋藩の上方交易港として、参勤交代時に藩主の船が出るところとして知られていました。明治時代~大正時代には、入郷地帯を後背圏とする物資の移出入港として栄えたのです。 今でも当時の建物、敷地割が残り、上方風の商家、操船・水運業者の家、漁家が連なり、とても貴重なので、1986年(昭和61)に、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。町並みは、虫籠窓や京格子をはじめ、通り庭風の土間に代表されるように、京都や大阪の町家造りを取り入れたものとして注目されます。その中で、市指定文化財「旧廻船問屋、元河内屋」(日向市歴史民俗資料館)、岡部家、矢野家、美々津軒などの古い家々を巡ってみるのも良いかと思います。
【美山】(みやま)京都府南丹市美山町美山町内には、たくさんの茅葺き民家が現存していますが、とりわけ北地区は、50戸の内38戸が茅葺き屋根の古民家で、昔ながらの村落景観を維持しています。そのことが評価されて、1993年(平成5)、周囲の水田と山林を含む集落全体127.5haが、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されました。この集落に現存している茅葺き屋根の家屋の多くが、江戸時代中頃から末期にかけて建てられたものであり、丈の高い入母屋造の屋根と神社の千木のような飾りが特色となっている「北山型民家」に分類されるものです。もともとは、林業を主産業とする山村集落で、中ほどを通る街道は、いわゆる鯖街道の一つとされ、京都と若狭の中間地であって、多くの旅人が行き来していました。三方を囲む山、清らかな由良川の流れがうまく調和し、農村の原風景を形造っていて、集落内の住宅は山麓の傾斜地を整地して建てられており、宅地正面には石垣を築いてあって、美しい景観を作っています。現在この地区では「かやぶきの里保存会」を組織し、歴史的景観の保全と住民の生活を両立すべく、さまざまな検討を重ねた結果、住民出資の「有限会社かやぶきの里」を設立し、建造物の維持管理および観光施設としての運営を組織的におこなっています。集落内には、交流館、民俗資料館、民宿があり、集落のはずれには、食堂、土産物屋などもあって、散策したり、宿泊したりすることもできます。
【温泉津】(ゆのつ)島根県大田市の温泉津は、戦国時代後期から江戸時代前期にかけて最盛期を迎えた石見銀山(大森銀山)の積出港でした。その後、明治時代には山陰航路の港で木材、竹材、石見焼を積み出したのです。また、発見されてから約1300年の歴史を持つ、湯治場として評判の由緒ある温泉地でもあります。昔ながらの旅館や豪商屋敷などが並ぶ風景は、明治、大正時代の雰囲気を色濃く残しているので、2004年(平成16)には、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。また、2007年(平成19)には、大森銀山と共に、「石見銀山遺跡とその文化的景観」として、世界遺産(文化遺産)に登録されたのです。中でも、元湯、薬師湯という2つの共同浴場と温泉旅館街、温泉津焼きの窯元や「やきもの館」、安楽寺、西楽寺、龍澤寺などを巡ってみると昔ながらの情緒があってとても良いと思います。
【脇町南町】(わきまちみなみまち)徳島県美馬市の脇町は、脇往還である撫養街道と讃岐街道が交わる交通の要衝で、江戸時代には藍の集散地として知られ、藍商人や呉服商などの家が軒を連ねて繁盛しました。富の象徴として立派な「うだつ」(防火用の袖壁)を載せる家が多くあり、通称「うだつの町並み」とも呼ばれるようになったのです。今でも、江戸時代中期〜昭和時代前期の伝統的建造物が、85棟残されていて、貴重な町並みなので、1986年(昭和61)に制定された「日本の道100選」に選定され、さらに、1988年(昭和63)には、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。町並みは本瓦ぶきの土蔵造りで、「うだつ」、格子造り、蔀戸、虫籠窓がその特徴となっています。中でも、吉田家住宅(市指定文化財)、「美馬市観光文化資料館」、小野五平生家(十二世将棋名人)、茶里庵、時代屋、オディオン座などを巡るとレトロな雰囲気の中にかつての繁栄を感じました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ご意見、ご要望のある方は右記までメールを下さい。よろしくね! gauss@js3.so-net.ne.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||