インデックス
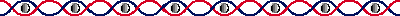
| 金沢城探訪マップ |
 |
金沢城(石川県金沢市)は、加賀百万石前田家の居城だったところで、国の史跡に指定され、石川門、三十間長屋、鶴丸倉庫が残っていて、国の重要文化財となっています。また、近年金沢城公園として整備され、菱櫓、橋詰門、橋詰門続櫓、五十間長屋、河北門が木造で復元されていて、見学できます。さらに、玉泉院丸庭園も復元されて、散策できるようになりました。尚、2006年(平成18)には、日本100名城にも選定されました。城下には、長町武家屋敷跡が残されていて、上流・中流階級藩士の侍屋敷が軒を連ね、内部が見学できるところもあります。
以前から、金沢城と言えば、石川門と言うくらいに有名ですが、現在の石川門は、1788年(天明8)に再建されたもので、国の重要文化財に指定されています。城の背面である搦手口(裏口)を守る搦手門で、外側に高麗門の一の門、内側に櫓門の二の門、そして、続櫓と二重の石川櫓で構成された枡形門です。兼六園と対になった位置にあり、橋で兼六園へと繋がっています。ライトアップされた姿がとてもみごとなのです。
 |
 |
| 河北門(復元) |
この門は、金沢城三の丸の正門にあたり、橋爪門、石川門と共に、「金沢城三御門」と呼ばれていました。金沢城の建物の大半が焼失した宝暦の大火(1759年)の後、1772年(安永元)に再建され、1882年(明治15)年頃まであったものを2011年(平成23)に、忠実に復元したものです。尚、枡形門形式になっていて、一の門と櫓門の二の門で構成されています。
 |
 |
| 菱櫓(復元) |
菱櫓は3層3階で、高さ約17mと二ノ丸で最も高い建物でした。名前が示す通り、櫓の平面と内部の柱を含めて、鈍角100度、鋭角80度の菱形となっています。初層は、唐破風の出窓、二層屋根は入母屋造りで、天守閣のなかった金沢城では、象徴的な櫓でした。橋爪門続櫓との間を2層2階の五十間長屋でつないでいるのが特徴です。
 |
 |
| 五十間長屋(復元)表側 |
五十間長屋(復元)裏側 |
菱櫓と橋爪門続櫓との間をつなぐ2層2階の多門櫓を「五十間長屋」と呼んでいます。武具や武器、什器等の倉庫として利用されていました。屋根は鉛瓦で葺き、海鼠壁になっていて、2箇所の石落があり、 2階へ上がると、太い松の梁等、木組を確認することができます。1881年(明治14)に焼失しましたが、2001年(平成13)に復元されました。全て木造で造られ、釘は一切使わない伝統工法で建てられています。
 |
 |
| 橋爪門一の門(復元) |
橋爪門二の門(復元) |
橋爪門は二の丸の正門にあたる枡形門で、河北門、石川門と共に、「金沢城三御門」と呼ばれていました。最も格式の高い門で、高麗門形式の一の門、石垣と二重堀で囲まれた枡形、櫓門の二の門からなっています。1809年(文化6)に再建され、1881年(明治14)に焼失したものをそのままの姿で、2001年(平成13)に一の門、2015年(平成27)に二の門、枡形二重堀が復元されました。
 |
 |
| 橋爪門続櫓(復元) |
橋爪門続櫓は、橋爪門枡形内を見張る物見の櫓です。この櫓の中央には、物資を2階へ荷揚げするための大きな吹抜けが造ってありました。1881年(明治14)に焼失しましたが、2001年(平成13)に復元されました。全て木造で造られ、釘は一切使わない伝統工法で建てられています。
 |
 |
| 三十間長屋 |
本丸の正面である鉄門前にある曲輪が附段ですが、そこに2層2階の多聞櫓の三十間長屋が立っています。1858年(安政5)の上棟で、長さは26間半(約40m)、大千鳥を中央に、唐破風を左右に配した出窓を持っていて、内部には、武器・武具が格納されていました。江戸時代から残る建物として、1957年(昭和32)に国の重要文化財に指定されています。
 |
 |
| 鶴丸倉庫 |
戌亥櫓跡 |
鶴丸倉庫は、幕末の1848年(弘化5)に建築された武具土蔵で、明治以降は、陸軍によって被服庫として使われていました。かつては、軍による建築と考えられていましたが、2000年(平成12)の石川県の調査によって、江戸時代後期の建築であることが判明したのです。これによって、2008年(平成20)には、国の重要文化財に指定されることになりました。城郭内に残っている土蔵としては、国内最大級の遺構で、総二階の延床面積約636m²(下屋除)とのことです。
⑨玉泉院丸庭園
玉泉院丸庭園は、城内に引かれた辰巳用水を水源とする池泉回遊式の大名庭園で、2代目藩主利長の正室玉泉院(永姫)が屋敷を構えたこがその名の由来とされています。3代目藩主利常が、1634年(寛永11)に京都の庭師剣左衛門を招き作庭したのが始まりでした。その後、歴代藩主が手を加えながら、廃藩時まで存在していたのです。明治期になくなり、戦後は石川県体育館が建てられていました。しかし、2015年(平成27)に発掘調査の結果に基づき、遺構を盛土保存した上で、江戸時代末期の姿をもとに再現されたのです。特徴としては、池底からの周囲の石垣最上段までの高低差が約22mもある立体的な構成であること、色紙短冊積石垣をはじめとする意匠性の高い石垣群などです。
⑩兼六園
 |
 |
| 徽軫灯籠 |
霞ヶ池 |
日本三名園の一つで、加賀藩の5代目藩主・前田綱紀が、別荘を建てその周辺を庭園としたのが始まりとされています。 その後、加賀藩前田家の歴代藩主により長い歳月をかけて形作られ、現在のような一大庭園となったのは1851年(嘉永4)とのことです。 1874年(明治7)より、金沢市民に開放され、1922年(大正11)、国の名勝に指定されました。そして、1985年(昭和60)には、名勝から
特別名勝へと格上げされています。特に、徽軫灯籠(ことじとうろう)付近から霞ヶ池を見た景色が有名です。
| 指定文化財 |
指定 |
員数 |
指定年月日 |
| 石川門 |
重要文化財 |
1棟 |
1935年(昭和10)5月13日 |
| 三十間長屋 |
重要文化財 |
1棟 |
1957年(昭和32)6月18日 |
| 鶴丸倉庫 |
重要文化財 |
1棟 |
2008年(平成20)6月9日 |
| 金沢城跡 |
史跡 |
1件 |
2008年(平成20)6月17日 |
| 兼六園 |
特別名勝 |
1件 |
1985年(昭和60)3月20日 |
◎金沢城の歴代城主(加賀前田家以降)
| 代 |
歴代城主 |
石高 |
在城年 |
備考 |
| 初代 |
前田利長(としなが) |
1,270,000石 |
1599~1605年 |
|
| 2代 |
前田利常(としつね) |
1,270,000石 |
1605~1639年 |
|
| 3代 |
前田光高(みつたか) |
1,025,000石 |
1639~1645年 |
|
| 4代 |
前田綱紀(つなのり) |
1,025,000石 |
1645~1723年 |
|
| 5代 |
前田吉徳(よしのり) |
1,025,000石 |
1723~1745年 |
|
| 6代 |
前田宗辰(むねとき) |
1,025,000石 |
1745~1746年 |
|
| 7代 |
前田重熙(しげひろ) |
1,025,000石 |
1746~1753年 |
|
| 8代 |
前田重靖(しげのぶ) |
1,025,000石 |
1753年 |
|
| 9代 |
前田重教(しげみち) |
1,025,000石 |
1753~1771年 |
|
| 10代 |
前田治脩(はるなが) |
1,025,000石 |
1771~1802年 |
|
| 11代 |
前田斉広(なりひろ) |
1,025,000石 |
1802~1822年 |
|
| 12代 |
前田斉泰(なりやす) |
1,025,000石 |
1822~1866年 |
|
| 13代 |
前田慶寧(よしやす) |
1,025,000石 |
1866~1871年 |
|

























