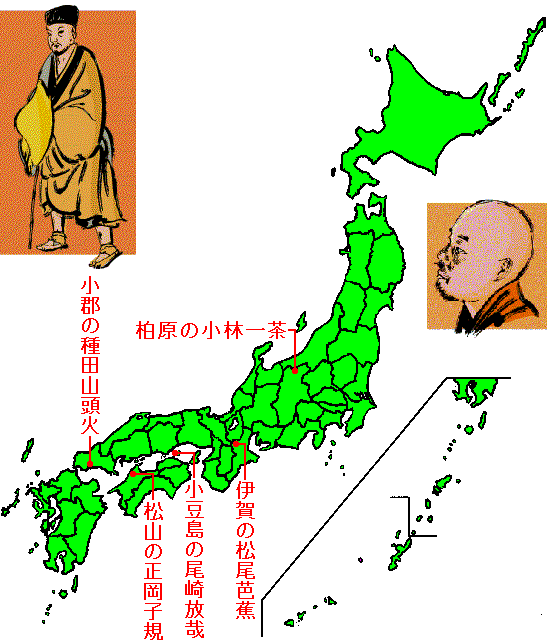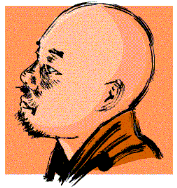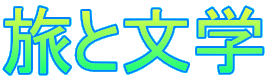 |
||||||||||||||||||||||||
| <旅 と 俳 句> | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
☆俳句を巡る旅五題
|
||||||||||||||||||||||||
|
私は、学生時代から各地を旅していますが、その中で特に心に残った俳句に関わる所を北から順に5つ紹介します。 (1)一茶の里のある柏原(長野県上水内郡信濃町) 江戸末期の俳人小林一茶の出身地で一茶記念館には遺墨、遺品等が展示され、全国を行脚した一茶の旅の様子を追想することができます。また、記念館のある小丸山公園の敷地内には1957年(明治43)に一茶を偲んで建てられた俳諧寺や一茶像、墓もあり、近くには史跡として小林一茶旧宅があって、生涯を閉じた土蔵が残されています。町内には、100基以上の句碑が建てられていますが、小丸山公園の一角にある『是がまあつひの栖か雪五尺』の句碑は印象的です。
(2)伊賀上野(三重県伊賀市) 言わずと知れた俳聖、松尾芭蕉の出生地で、29歳までこの地で過ごしました。その生家跡や遺髪を収めた故郷塚、俳聖殿、「芭蕉翁記念館」などがあって、足跡をたどることが出来ます。特に、服部土芳の「蓑虫庵」は、芭蕉五庵の一つで、当時の建物が残り、風情が保たれていて、往時を忍ぶことができます。苔むした庭には、芭蕉の『古池や 蛙飛こむ 水の音』、『みの虫の 音を聞ばやと この庵』、『よく見れば なづな花咲く 垣根かな』などの句碑があり、芭蕉の声が聞こえてきそうな感じさえします。
(3)小豆島の南郷庵跡(香川県小豆郡土庄町) 俳人尾崎放哉が庵主として最後の8ヶ月を過ごした終焉の地で、墓もあります。庵の跡には、1994(平成6)年4月「小豆島 尾崎放哉記念館」が開館、貴重な資料が展示され、庭には句碑も建てられています。放哉は、東京帝国大学法学部卒業のエリートでありながら、身を持ち崩し、いくつかの寺を転々として、最後にたどり着いたのがこの小豆島でした。しかし、自由律俳句の天才で、斬新な歌を詠みました。病魔と闘いながらの最後には、感銘深いものがあり、42歳で逝った生涯を追想すると、胸にこみ上げてくるのを感じました。良く知られている句は、『咳をしても 一人』、『入れものがない 両手で受ける』、『足のうら洗えば白くなる』、『春の山のうしろから 烟が出だした』などです。
(4)子規堂(愛媛県松山市) 明治時代に俳句・短歌革新を訴えて、活躍した正岡子規の旧宅を正宗寺境内に復元したもので、遺品、遺墨等を見ることができます。子規が幼年期を過ごした3畳間があって、その風貌が浮かんできます。また、道後公園には市立子規記念博物館があり、豊富な資料を公開しています。他に、河東碧梧桐、高浜虚子などが出ていることもあって、市内には600もの句碑が点在しています。松山城にある『松山や秋より高き天守閣』の子規句碑は有名です。
(5)其中庵(山口県山口市) 放浪の俳人種田山頭火が、安住の地を得ようとして、庵を結んだところで、その「其中庵」が復元され、近くの町立資料館には山頭火展示室もあります。山頭火は、日本全国を行乞しながら、自由律俳句といって、五七五にとらわれない自由な句を詠んだ俳人です。「其中庵」は、以前ほんとうにわびしい茅葺きの家だったらしいけど...。なんだか、そこにたたずんでいると山頭火の心境が分かるような気がしました。良く知られている句は、『後ろ姿の しぐれていくか』、『どうしょうもない わたしが 歩いている』、『分け入っても 分け入っても 青い山』、『さて、どちらへ行かう 風が吹く』などです。
|
||||||||||||||||||||||||
*いくつわかりましたか? 解答はこちらです。 |
||||||||||||||||||||||||
*ご意見、ご要望のある方は右記までメールを下さい。よろしくね! gauss@js3.so-net.ne.jp |


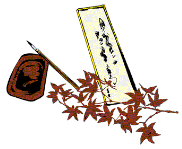 ☆句碑のある風景
☆句碑のある風景