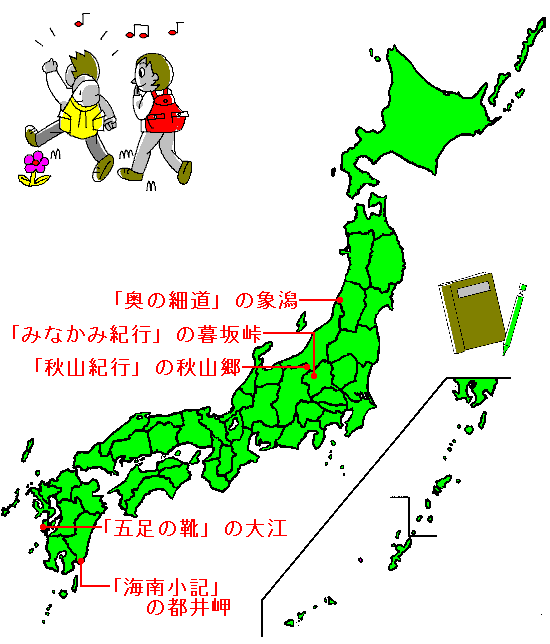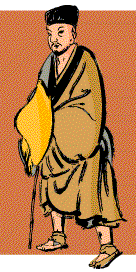�u���̃z�[���y�[�W�v�́A���낢��ȍ������s����Ƃ���z�[���y�[�W�ł��B
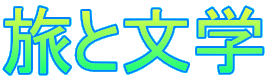 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���� �� �I �s ���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���I�s�������闷�ܑ�
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@���́A�w�����ォ��e�n�𗷂��Ă��܂����A���̒��œ��ɐS�Ɏc�����I�s���Ɋւ�鏊���T�A�k���珇�ɏЉ�܂��B�B �i1�j�ۊ��i�H�c���ɂ��َs�j �@�I�s���̔����A�����m�Ԓ��w���̍ד��x�̖ړI�n�̈�ŁA�����͏����ƕ��я܂���闠���{�̌i���n�ł����B���̌�A1804�N�i�������j�̏ۊ��n�k�ŗ��N���A���X�͗��n�Ɖ����Ă��܂��A�i�ς���ς��Ă��܂��܂����B���ł́A���X�͐��c�̒��̏��R�ƂȂ��Ă��܂����A������E�Ԃ��Ƃ��o���܂��B�m�Ԃ��K�ꂽ�s�����ɂ́A�w�ۊ���J�ɐ��{���˂Ԃ̉ԁx�̋�肪����܂��B
�i2�j�H�R���i���쌧�h���E�V�����Ó쒬�j �@�w�k�z�ᕈ�x�Œm����]�ˎ������̉z��̕��l��ؖq�V���A�\�ԎɈ��̊��߂ŏ������w�H�R�I�s�x�Ƃ����I�s��������܂��B1828�N�i����11�j�H�ɁA�H�R���̑��X���U���V���ŏ��������̂��Ƃ����������̂ł��B�R���̎��R�╗�y�A�l�X�̈ߐH�Z����d���ɓ���܂ŁA�ڍׂɋL�^���A�����w�̐��Ƃ����Ă���̂ł��B�S���\�N�O�̂��̂ł����A���R�̗l�q�͂��܂�ς���Ă��Ȃ��悤�ɂ��v���A�ƂĂ������[���̂ł��B�ʼn��̏W���A�ؖ��̉���̗l�q���L�ڂ���A���ł��͌��Ɍ����@���ē�����ԂɁA�Â��f�����Ƃ��ł��܂��B�܂��A��쌴�ɂ́A��ؖq�V�Ɉ���ő���ꂽ�u�̂悳�̗� �q�V�̏h�v�Ƃ����̂�����A���̓����̏H�R���̕�炵�ƕ������Č������A�{�Ƃ�400���̘L���Ō���Ă���V�˂̕��Ƃō\������Ă��āA�ʔ����{�݂ł��B
�i3�j��⓻�i�Q�n�����V�j �@��R�q����1922�N(�吳11)�̗��̓r���ŁA��i�F�̒����q�ƂQ�l�k���ʼnz�����Ƃ���ł��B���̎��̗����w�݂Ȃ��I�s�x�Ƃ��Ĕ��\����A�q���̑�\�I�ȋI�s���Ƃ��Ēm���Ă��܂����A�����A���̓r���ʼn̂��������̒Z�̂��U��߂��Ă��܂��B���É����⓻���z����n����Ɏ��铹�[�ɂ͂��̉̔肪�������Ă��A���R�����悭�c����Ă��āA�����̗���Ǒz�����鏊�ł��B�ʂɁA���̎��̈�ۂ��r�����u�͖�̗��v�Ƃ��������c����Ă��āA����������h�Ȏ���Ɩq���̗��p�̑����A1957�N�i���a32�j���ɗ����܂����B�q�����ʂ���10��20���ɂ͖��N�����ŁA����Ȗq���Ղ��Â����Ƃ����܂��B
�i4�j��]�V�哰�i�F�{���V���s�j �@�I�s���w�ܑ��̌C�x�̗��S�̂̃N���C�}�b�N�X�ŁA8��8���ɓV���������C�݂ŁA��s�i�^�Ӗ슰�A�k�����H�A�؉��ۑ��Y�A�g��E�A���얜���|�|�ܑ��̌C�Ƃ����Ă���j����J���ĕ��������̈ꕔ���A���w�V�����Ƃ��Ďc����Ă��܂��B��]�V�哰�͌��ĕς��܂������u�̏�ɂ��т��A���ӂɂ́A��s���K�˂��K���j�G�_���̕�⋹�������Ă��Ă��܂��B�V�哰�̘e�ɂ͋g��E�̉̔肪����A���̗�����z���āA�u���B�ƂƂ��ɔ��肵�V���̑�]�̏h�͔��V�A�̏h�v�ƍ��܂�Ă��܂��B���݂ł́A�V�哰�ɗאڂ��ēV�����U���I�ق����Ă��A�V���̋��ɖ������L���V�^���̗��j���w�Ԃ��Ƃ��ł��܂��B
�i5�j�s�䖦�i�{�茧���Ԏs�j �@�����ɂ́A���{�����w�̎����҂Ƃ�������c���j���A1920�N�i�吳9�j12���ɂ킴�킴�쐶�́u���n�i�݂������܁j�v�����ɗ�����������Ƃ��A�I�s���w�C�쏬�L�x�ɏ�����Ă��܂��B����C�ݍ�������̓�[�ɂ�����A�����m�ɓ˂��������������Z�̒n�ŁA�쐶�����̕�ɂƂ��Ȃ��Ă��āA�����e�A���A�K�Ȃǂ̎p�����邱�Ƃ��o���邻���ł��B�������A�Ȃ�Ƃ����Ă����n���������Ă��邱�ƂŗL���ł��B���̐�[�ɁA�����̎p��������̂��A�s�䖦����ŁA�����̊ό��̃V���{���Ƃ��Ȃ��Ă��āA�Y��ȑ����m��]�ޒ��]�Ɓu���n�v�́A�i�D�̔�ʑ̂ƂȂ�܂��B���̔n�́A�̍���130�p�Ə����ŁA�r�̊��ɂ͓����ŁA����Ƃ����̂��ł��B�n�������͂�ł���p�����������łق̂ڂ̂Ƃ����C���ɂȂ��̂ł��B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@�������킩��܂������H�@���������ł��B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����ӌ��A���v�]�̂�����͉E�L�܂Ń��[�����������B��낵���ˁI�@gauss@js3.so-net.ne.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


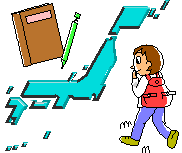 ���I�s���Ƃ́H
���I�s���Ƃ́H